おうち英語界隈ではよく「難しすぎる動画を見せても意味がない」と言われる。
でも、実際に子供に任せてみたら全然そんなことはなかった。
大事なのは英語のレベルの易しさではなくて、精神年齢と興味に合っているかどうか。
子供が「知りたい!」と思えば、Triassic(三畳紀)やCretaceous(白亜紀)だって自然に覚えてしまう。
難しいかどうかは大人のモノサシでしかなく、子供にとっては当たり前の言葉になることもある。
難しすぎる動画を見せてみたら…
我が家の場合、「ネイティブの若者が弾丸のように喋るゲーム実況動画」がきっかけだった。
どう考えても難しすぎるだろうと思ったけど、ちょうどマインクラフトにハマっていた時期で、アイテムや攻略法を知りたい気持ちが強かったから、夢中になって観ていた。
「映像だけ見てるんじゃないの?」と心配になる人もいるかもしれない。
でも、興味があればちゃんと聞いている。英語を聞いているという意識すらなく、必要な情報として受け取っていたように思う。
吸収していた証拠
そのインプットは、すぐにアウトプットにつながった。
兄弟でマイクラを遊ぶときは英語で会話しているし、あの実況動画がなければ、ここまで話せるようにはならなかったと思う。
しかも、ゲームだけにとどまらない。
小4の息子は宇宙の話が好きで、現代宇宙論のような私ではついていけない内容を英語で語ってくる。
すると夫が日本語で返すという、不思議な英語×日本語の対話が始まることもある。
学校では出てこない単語も自然と覚える
こうした経験を通じて、日本の学校英語とのギャップを強く感じる。
例えば random。日本語だと「無作為」ぐらいの堅い意味でしか使わないけど、英語では「なんか適当」とか「よく分からんけど」といった日常の場面で頻繁に使われる。子供はゲーム実況から自然に覚えて、実際に使っている。
マインクラフトなら emerald(エメラルド)、obsidian(黒曜石)、quartz(水晶) など、学校では絶対出てこない単語を普通に知っている。
さらに butt のように、学校ではまず習わないけれど実生活ではよく出てくる単語まで理解してしまう。
親として意識したこと
私が意識したのは、「自分で選んだ動画を観る」というスタンスを持たせること。
親が制限をかけず、子供が自分で選んだものだからこそ、強い興味を持って観る。やらされ感がないから、定着も自然に起こるのだと思う。
まとめ:難しすぎても意味はある
振り返ってみると、「難しすぎる動画を見せても無駄じゃなかった」と思う一番の理由は、子供が好きなものを語れるようになったこと。
英語がただの教科ではなく、思考の言語として身についていった。
日本ではよく「セミリンガルになるのでは?」と心配されるけれど、実際にはそうはならなかった。
むしろ、英語も日本語も「自分の世界を広げるための言葉」として根づいている。
だから私は、「難しすぎるから意味がない」という考え方こそ、ちょっともったいないなと思っている。

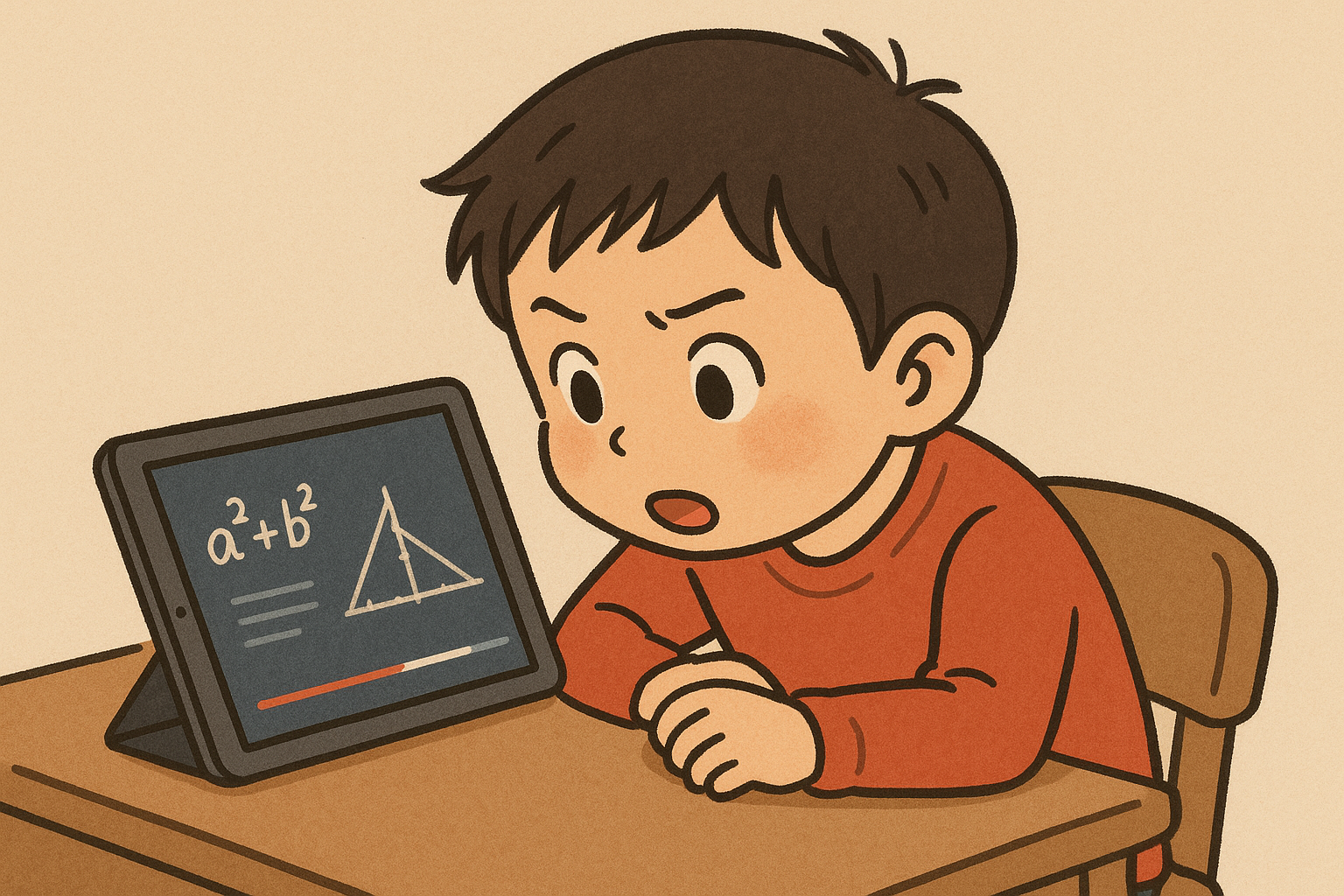


コメント