「フォニックスはちゃんと教えたほうがいい?それとも自然に任せて大丈夫?」と迷う親は多いと思う。私は、フォニックスらしい取り組みはリープフロッグのDVDくらいしかしてこなかった。それでも長男はNetflixの英語字幕から自然に文字と音の法則を見つけて読めるようになっていたし、次男もepic! の漫画を読む中で徐々に文字に慣れていった。ここでは、その実体験をベースにしつつ、科学的な視点も足して、家庭でフォニックスをどう捉えるかを整理してみる。
フォニックスの基礎:何を「基礎」と呼ぶか
フォニックスは、アルファベットと音を結びつける学習法の総称だと私は捉えている。まず土台になるのが、文字と音の対応(letter–sound correspondence)。例えば “A” は /æ/(日本語の「ア」に近い)、“B” は /b/(「ブ」)、“C” は /k/(「ク」)のように対応を知る段階だ。ここから、音をつないで読むブレンディング(例:c–a–t → “cat”)や、“au” が「オー」と読まれるような綴りパターンなど、より広い規則の理解へと進んでいく。
我が家で使った教材と反応
本格的に取り入れたのはリープフロッグ(LeapFrog)シリーズのDVD。文字と音の関係やブレンディングをアニメと音楽でテンポよく見せてくれるので、2人ともよく食いついていた。YouTubeでフォニックス系の動画も探したけれど、うちではピンとくるものが見つからなかった。ナンバーブロックスの姉妹番組アルファブロックスも試したが、ナンバーブロックスほどの熱中はなかった、というのが正直なところだ。
長男:文字好きだから自然に法則を発見
長男は小さい頃から文字への興味が強く、2歳の時には無理に教えなくても平仮名もカタカナも読めていた。英語でも同じで、保育園の頃にNetflixの英語字幕をオンにしていたら、自然と音と文字の法則を見出して読めるようになっていた。理屈で押し込む前に、自分で規則を見つけてしまうタイプなのだと思う。
次男:遅れても、結局読めるようになった
一方の次男は文字認識に時間がかかった。公文で何年もひらがなに取り組んでも、しっかり読めるようになったのは小学校直前。英語もなかなか読めず、本人にコンプレックスめいたものも見えた時期があった。それでも、epic! の漫画を読む体験を積み重ねていくうちに、無理にフォニックスを叩き込まなくても、気づけば読める範囲が広がっていった。
科学的に見た「自然習得」の仕組み
なぜ、体系的にフォニックスを入れなくても読めるようになることがあるのか。私は次のように理解している。
- 統計的学習(Statistical Learning):人は繰り返し触れるうちに、音や文字の出現パターンを無意識に学ぶ。読みにくい状況でも、文字と音の規則性を拾い上げられることが示されている[注1]。
- 文字音知識の重要性:幼児期に「文字と音の対応」をどれだけ理解しているかは、その後の読み・書きの発達を予測する要因になるとされる[注2]。だから、まずは基礎の対応だけ押さえておく意義が大きい。
- 音韻認識(Phonological Awareness):言葉を音の単位に分けたり、つなげたりする力は、解読(decoding)の土台になる。フォニックスの練習と親和性が高い概念だと感じている[注3]。
- 明示的指導と自然習得の両立:すべてのルールを小さいうちに網羅的に教え込む必要は必ずしもない。基礎の文字音対応と、絵本・漫画・字幕などの豊富なインプットがあれば、自然に法則を身につけていけるケースは多い[注4]。
私が出した結論:基礎はやる、先は体験で伸ばす
我が家の経験からは、基礎の文字音対応はやっておいたほうが良いと感じている。一方で、ブレンディングや綴りパターンなどの先のフォニックスを、小さいうちからゴリゴリにやる必要はない、とも思う。人間の脳は、楽しいインプットの積み重ねから規則を見つける力が強い。だからこそ、絵本・漫画・字幕のように子どもが「面白い」と感じる形で触れる時間を担保するほうが、結果的に伸びると考えている。
「理論の面白さ」は後からでも楽しめる
私は子どもの頃にフォニックスを体系的に学ばずに育ち、大人になってから理論を知って「へぇ、英語ってこう動いていたのか」と感動した。だから、息子たちにももう少し大きくなったら、トリビア的に知識として触れさせたい。日常的には体験ベースで伸ばし、知識としては後から整理しても十分に面白いし、むしろ腹落ちする気がしている。
まとめ
- フォニックスの基礎(文字と音の対応)は押さえる。
- その先の細かいルールは、読書・漫画・字幕などの楽しいインプットで自然に身につくことが多い。
- 子どものタイプや興味に合わせて、どこまで明示的に教えるかを柔軟に決めれば十分。
- 理論は大きくなってから知識として学び直すのも面白い体験になる。
注釈・参考文献
[注1]Apfelbaum, K. S., Hazeltine, E., & McMurray, B. (2013). Statistical learning in reading: Variability matters. Developmental Psychology, 49(7), 1340–1352. リンク
[注2]Bigozzi, L., Tarchi, C., Pinto, G., & Donfrancesco, I. (2022). Letter sound knowledge as a predictor of reading and spelling. Early Childhood Research Quarterly, 59, 119–128. リンク
[注3]Phonological Awareness – Wikipedia. リンク
[注4]Principia Learning. (2021). Do all phonics rules need to be explicitly taught? リンク

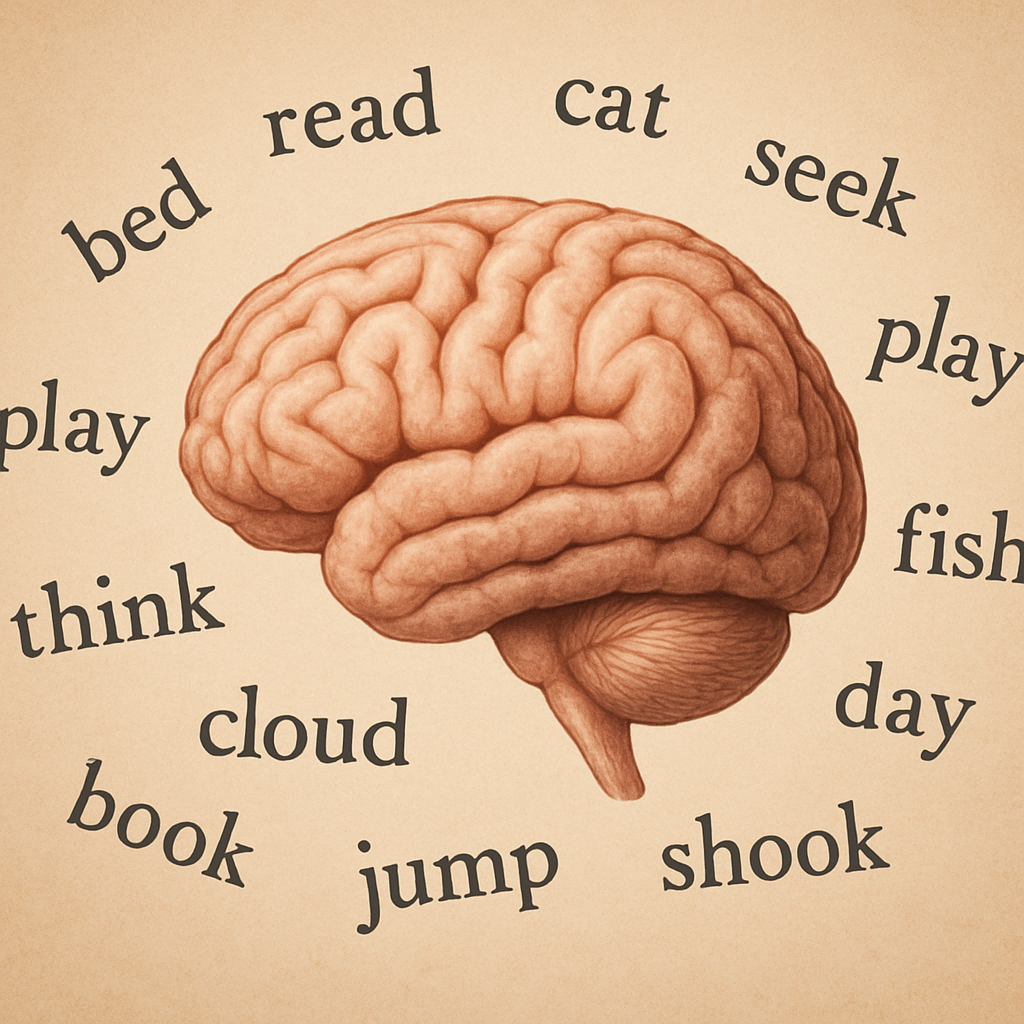


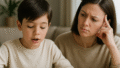
コメント