私は普段、「勉強しなさい」とは言わない方針でやっている。ただ、それだけだと勉強に興味を持つきっかけが足りないかもしれないと感じて、今回だけは珍しく「この本を読んでみて」と『小学生のタイパUP勉強法』というハウツー本を小4息子に手渡した。ねらいは、言われたままの学習をやっつけで取り組むのではなく、勉強方と記憶の関係や成果の出し方に興味を持って欲しかったからだ。
なぜこの本を渡したのか
この本は、多くの勉強法本のように親や先生向けではなく、子供本人に向けて書かれているのが大きな特徴だ。だからこそ、自分ごととして受け止めやすく、親が口で説明するよりも素直に響くのではないかと思った。
私は、親が説得して回すより、子供が自分で納得して回す方が長持ちすると思っている。そこで、勉強の型を押し付けるのではなく、脳の使い方に目を向ける足場としてハウツー本を使ってみた。
家でしている“記憶の話”との相性
エビングハウスの忘却曲線の動画はよく見せているし、短期記憶と長期記憶の違いも意外と理解している様子だ。「忘れるのは普通」「思い出す練習が記憶になる」という感覚が少しずつ腹落ちしてきている。だから今回の本も、どう実践に落とすかのヒント集として吸収してほしいと考えた。
本から拾った“記憶ベース”の実践ネタ
本の中で印象的だったのは、人に説明することで理解が深まるという考え方だった。単に問題を解き直すより、誰かに教えるつもりで話す方が、自分が本当に分かっている部分と分かっていない部分がはっきりする。
小4息子の場合は、弟に向かって「これってね、こういうことなんだよ」と説明するのが楽しいらしく、自然と自分の復習になっていた。説明している途中で言葉に詰まったら、それが理解の穴だと気づける。教える=自分の頭の中を整理する練習として、取り入れやすい方法だと思った。
小4息子に起きた小さな変化
「どうせ忘れる」ではなく、「忘れる前提で、いつ思い出すか」を気にするようになった。復習を“やり直し”ではなく“再生のゲーム”として扱えると、本人の機嫌がだいぶ違う。結果として、自分からタイマーをセットして10分だけ回す、といった小さな自主運転が増えた。
親が説得するより“仕組み”を渡す
親が「復習しなさい」と言っても刺さらないことがある。でも、人はこうやって忘れ、こうやって思い出すという仕組みに触れると、子供は自分でやり方を組み替え始める。私は、ここに本の価値があると感じた。正しいフォームを教えるより、思考の土台を渡すイメージだ。
まとめ
小学生に勉強法本は早いかなと思っていたけれど、記憶の扱い方に気づく導線としては相性がよかった。ノートを完璧にするタイプでなくても、「思い出す練習をどこに差し込むか」だけ決めれば回り始める。私は、親が説得を重ねるより、子供が自分の脳の使い方を知って工夫することが長い目で効くと感じている。

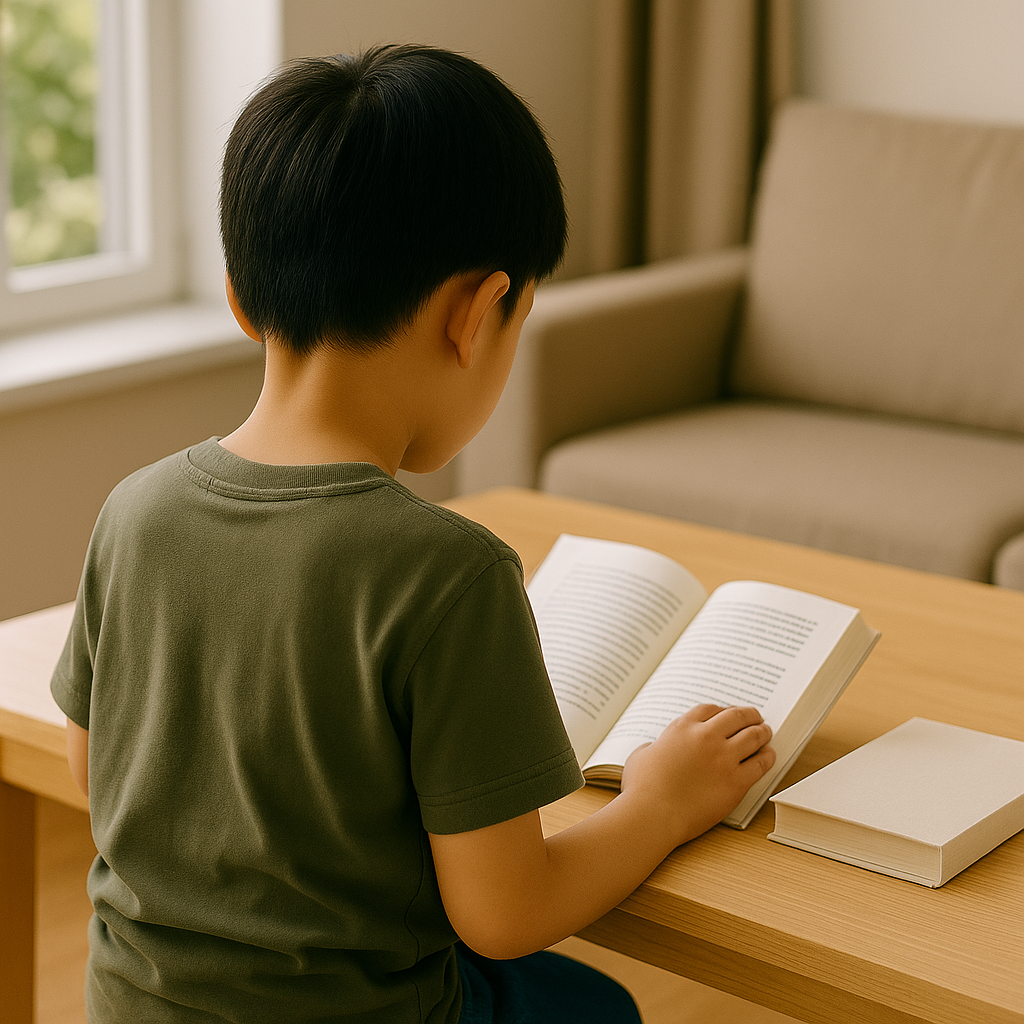



コメント