「国語が苦手」という自己認識を持った小4の息子。テストやドリルを通じて見えてきたのは、漢字力そのものではなく、日本語の語彙不足という課題でした。なぜそうなったのか、そしてどのように取り組んでいるのかを、いったん冷静に整理してみようと思います。
語彙が不足していた理由(我が家の環境要因)
振り返ってみると、本人の能力というよりインプット環境の偏りが大きかったな、と感じています。
- 普段ほとんどテレビをつけない → 受け身の日本語インプットが少ない。
- YouTubeは本人に選ばせている → ほぼ英語コンテンツを選ぶため、日本語に触れる機会が限られる。
- 日本語の本はあまり自分から読まない → 「本は楽しむもの」というスタンスで強制しなかった。
その結果、「態度」「きっかけ」といった抽象語の日本語だけが抜け落ちがちになり、英語の attitude や motivation ならすぐ通じる、というギャップが見えるようになりました。
漢字ドリルで見えた“つまずき”の正体
漢字自体は書けても、言葉の意味が入っていないため、文脈の中で適切な字を選べない場面が多いと気づきました。日本語は同音異義語が多いので、語彙の理解が浅いと正答にたどり着けないことがあるんだな、と。
テストを分析して、戦略を転換
いったん「無理かも」と諦めかけたのですが、テストを細かく見ると教科書に出た熟語がそのまま出題される傾向が強いと分かりました。そこで方針を切り替えました。
- 教科書準拠のドリル・問題を中心に反復する。
- まずは丸暗記でOKと割り切る(英単語学習も初期は暗記中心だし、同じだと捉える)。
- 同じ範囲を短期集中で繰り返し、語の「使われ方」を体に入れる。
短期反復の効果:壊滅的→8割以上
同じ問題(例:1学期の範囲)を2〜3日繰り返し解かせたところ、最初は壊滅的だった正答率が、最後は8割以上まで改善しました。ここで「国語もやればできる」という手応えが本人に生まれたのは、とても大きかったです。
二学期の進め方(当面の目標)
いきなり“日本語全体の底上げ”を狙うより、まずは学習の成功体験を積ませる方が現実的だと考えています。二学期は次の方針でいきます。
- 学校の範囲をがっちり固める(教科書準拠で土台づくり)。
- 準拠問題集を増やし、例文のバリエーションを広げる(同じ熟語でも文脈が変わると“使い方”が見えてくる)。
- 見たことのない使われ方が出ても、共通点から推測できるようにする。
日本語の本は「楽しむためのもの」として残す
以前は「日本語の本を読ませなきゃ」と焦っていましたが、今は漢字学習を語彙強化の軸に据えています。本は本来たのしむものなので、強制はしない方針で。読みたい気持ちが自然に育つまで、学習のルール化がしやすい漢字から地力を上げていくつもりです。
さいごに(いまの見立て)
小4息子の「国語が苦手」は、漢字の筆順や画数の問題ではなく、語彙のインプット不足が正体だった、と私は見ています。英語側では思考がきちんと回っているので、いわゆる“ダブルリミテッド”というより、日本語の入力が足りていない一時的なアンバランス。まずは反復学習で成功体験を積み、「やればできる」という自己肯定感を足場に、少しずつ日本語の地盤を広げていけたらいいな、と思っています。


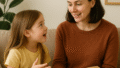
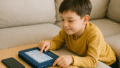
コメント