小1の壁とは何か
小学校に上がるとき、おうち英語をしている家庭なら誰もが気にするのが「小1の壁」だと思います。
せっかく幼児期に積み上げてきた英語の習慣が、このタイミングで崩れてしまうのではないか。そんな不安を感じる親は少なくないはずです。
巷で言われる「小1の壁」とは
おうち英語界隈でよく言われる「小1の壁」とは、小学校入学を境に英語の習慣が途切れやすくなる現象を指しています。
- 学校の宿題や生活リズムで英語に触れる時間が減る
- 友達とのやりとりが日本語中心になり、英語より日本語を優先する
- 英語を「やらされている」と感じ、抵抗が強まる
家庭で築いてきた英語環境が、日本語社会に一気に押し戻されてしまう。これが「小1の壁」と呼ばれる現象です。
わが家には「壁」が来なかった
ただ、わが家のケースは少し違っていました。
小1になった次男には、その「壁」がまったく訪れなかったのです。むしろ英語が自然に出てくるようになり、「ペラペラ期」に入ったと感じています。
なぜそうなったのか。その理由を振り返ってみます。
小1の壁がなかった理由
1. 友達よりもゲーム・動画に夢中だった
多くの子どもは友達と遊ぶために日本語を使う時間が増えます。
しかし、次男の場合は同級生とのやりとりよりも、YouTubeやゲームへの関心が強かった。(それもどうかと思いますが。。)
しかもそれらは英語前提のコンテンツだったため、自然と日本語より英語に触れる時間が増えていったのです。
2. 兄弟間の共通言語が英語だった
小4の長男と小1の次男は、家庭内で一緒に遊ぶ時間が多い。
共通の話題をやりとりする際、英語の方がスムーズに通じる場面が多く、兄弟間の共通言語として英語が定着していました。
3. 英語が「学習」ではなく「ツール」だった
英語を「勉強」としてやるのではなく、ゲーム攻略や動画理解に必要なツールとして使っていました。
やらされるものではなく、自然に使うものになっていたことが大きな違いでした。
一般論との違い
一般的に言われる小1の壁は、
- 友達との関わりが日本語中心になる
- 英語に触れる時間が減る
こうした流れで起こります。
一方、わが家の場合は、
- 友達よりも趣味や兄弟との関わりが多かった
- その接点が英語ベース
という構造になっていたため、英語が後退するどころか、むしろ強化される結果となったのです。
まとめ
小1の壁はすべての家庭に必ず訪れるわけではありません。
子どもの特性や家庭の環境によっては、むしろ「小学校入学=英語がジャンプアップする時期」になることもあります。
小1次男と小4長男のケースは、その一例だと思います。
英語を「学ぶもの」ではなく「使うもの」として根付かせることができれば、小学校生活の始まりは壁ではなく、新しいステージに進むきっかけになるはずです。
とはいえ、母としては、友達との関わりをもっと増やして欲しいなと思うのですけどもね。兄弟仲が良過ぎて困ります。

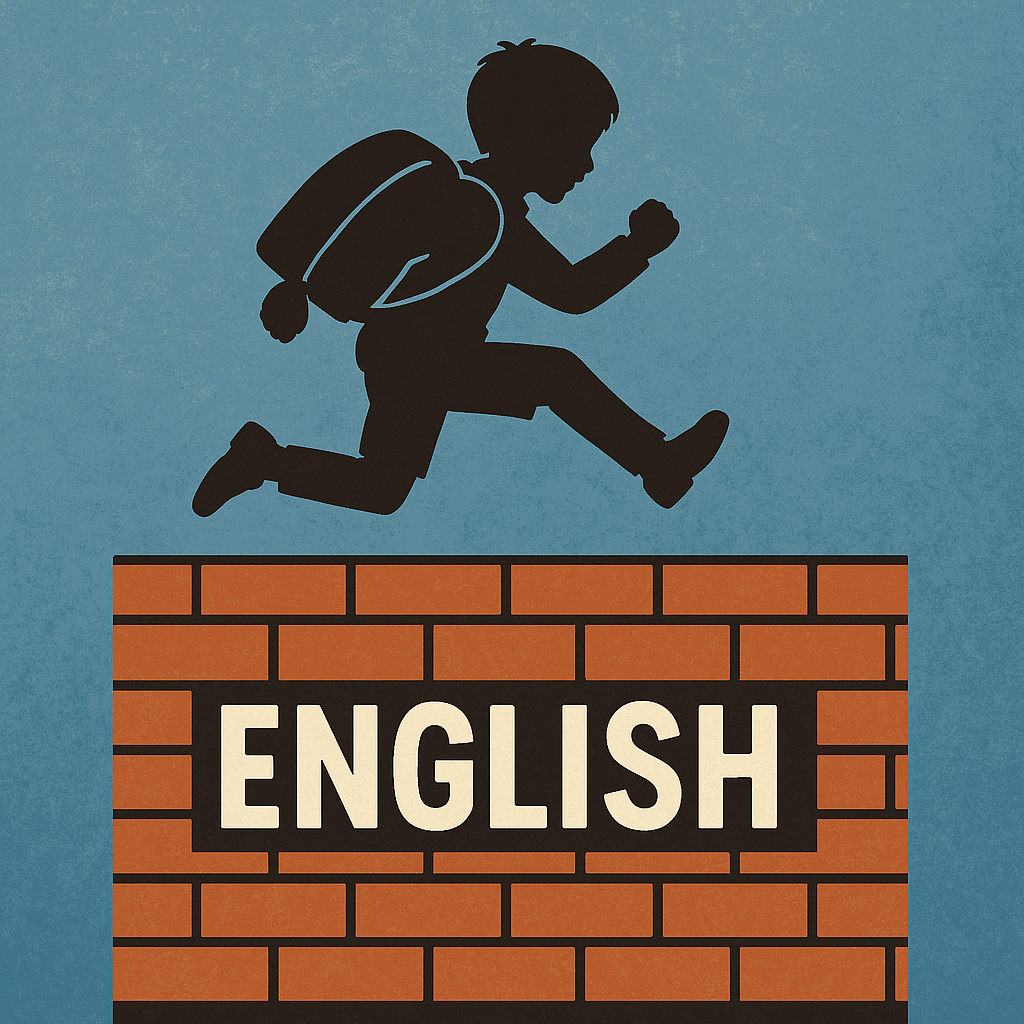


コメント