本屋の学習参考書コーナーで、市販ドリルを前に母娘が相談している場面を見かけた。「これやれば?」「こっちの方がいい?」そんな会話の中で決まっていく選び方は、実は多くの家庭でよくある光景だと思う。
市販ドリルは手軽で便利な一方、選び方や進め方によっては効果が薄れてしまうことがある。なぜなら、体系的な学習計画を立てにくく、場当たり的になりやすいからだ。
市販ドリルのメリット|子どもが楽しめるデザインも豊富
- 値段が手頃で始めやすい
- 計算・漢字・読解など分野別に豊富な種類が揃っている
- 公文や学研、ベネッセ、Z会など出版社ごとの特色がある
- うんこドリル、ちいかわ、マインクラフト、ポケモンなど、子どもが興味を持ちやすいデザインのものも用意されている
特に「弱点をピンポイントで補強したい」ときには、市販ドリルは強い味方になる。
市販ドリルのデメリット|計画性がないと続かない
- 多くのドリルは「毎日1ページで1〜2か月で終わる」設計
- 1冊終わるごとに次を探す必要がある
- 結果的に「似たようなドリルを繰り返す」ことになりやすい
親が年間の学習を俯瞰して設計しない限り、場当たり的な学習になってしまう。子どもからすると「親の気まぐれで選ばされたドリル」という感覚になりやすく、信頼感を持ちにくいのも難点だ。
市販ドリルと通信教育どっちがおすすめ?年間カリキュラムの違い
通信教育(進研ゼミ、Z会、ポピーなど)は、年間を通じての学習カリキュラムが組まれている。毎月の教材が届く仕組みになっているため、親が「次はどのドリルを買おう?」と迷う必要がない。
- 通信教育:体系的・計画的に進めやすい/習慣化しやすい
- 市販ドリル:自由度が高いが、親の管理力が問われる
どちらも一長一短だが、市販ドリルで子ども自身が計画性を持って進めるのは難しい。仮に計画的に取り組めても、それは一冊の範囲にとどまる。年間を通して学習計画を立てるのは小学生にはまず不可能だ。だからこそ、市販ドリルを活かすには親の設計が必須。一方、通信教育には最初から年間設計があるので任せやすい。
我が家はスマイルゼミ+教科書ぴったりトレーニングで体系的に学習
通信教育はスマイルゼミを選んだ。コアトレでは先取りにも復習にも対応でるし、毎月配信される講座は年間カリキュラムがしっかりしている点が安心材料。子どもが「今どこまで進めばいいか」に迷わず取り組める。
加えて、教科書準拠のワークは教科書ぴったりトレーニング(ぴたトレ)を併用している。教科書ワークとぴたトレ、どちらも良い教材だと思うが、我が家は解答が見やすいという理由でぴたトレを選んだ。紙に書く行為も少しは入れたいし、学校の授業に沿った内容をさらに強化すると「できた」という実感が得やすいことから、自己肯定感にもつながりやすい。
まとめ|市販ドリルはおすすめだが、使い分けと設計がポイント
市販ドリルはコスパが良く、興味を引くデザインも多いのでおすすめ。ただし、親が年間設計を持たないと場当たり的になりやすい。通信教育は最初から体系があるので、日々の迷いが少ない。我が家はスマイルゼミ+教科書ぴったりトレーニングで、デジタルの進めやすさと紙の定着感を両立させている。この組み合わせが今のところしっくり来ている。

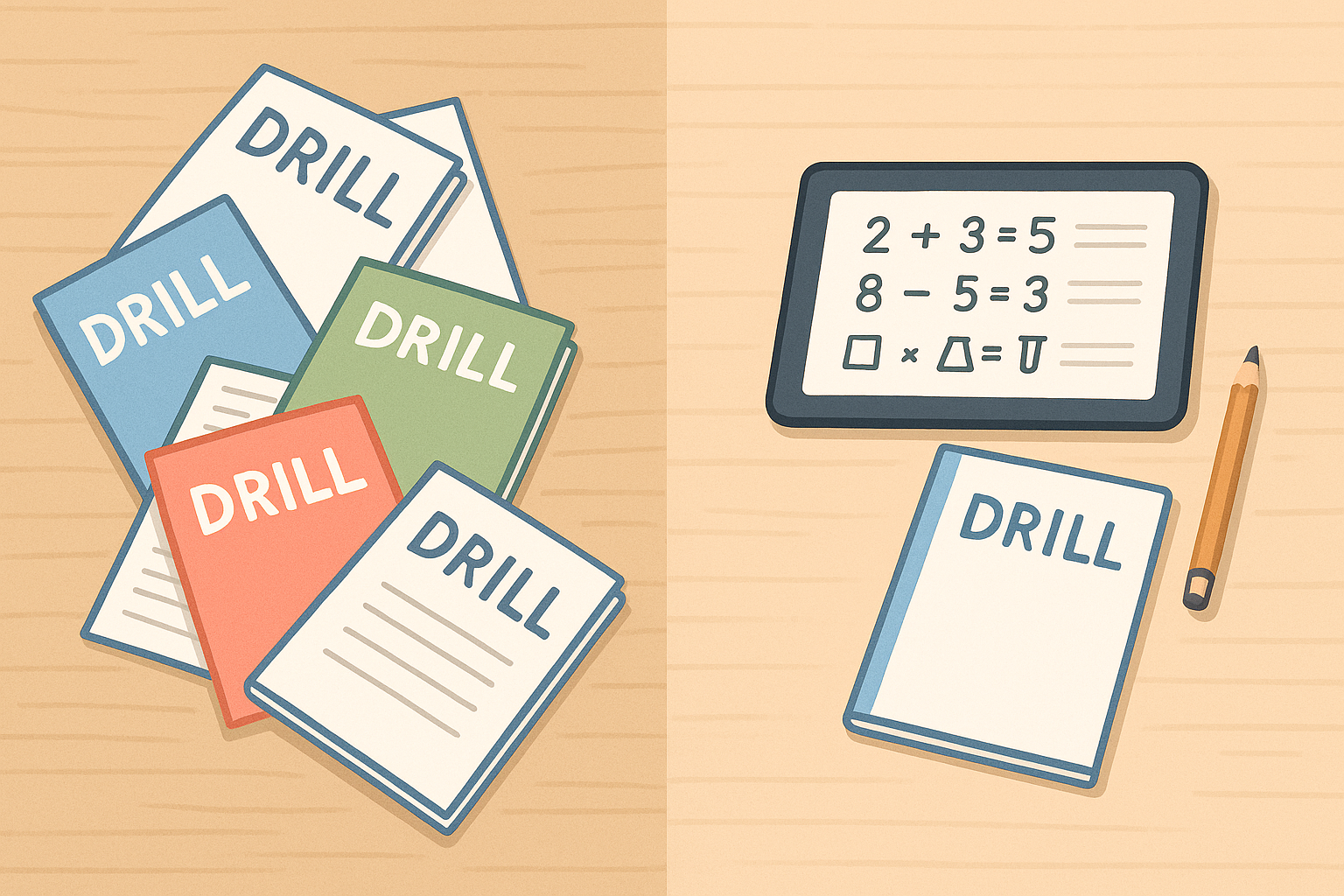


コメント