「おうち英語って、やるなら0歳からじゃないとダメなんじゃない?」
そんな空気を感じたことがある人もいるかもしれない。
我が家も、そんな“常識”にちょっと焦った時期があった。
しかし実際には、長男が4歳、次男が2歳半のタイミングでスタート。
いわゆる「遅めのスタート」だった。
この記事では、我が家のおうち英語の始まりと、その後の変化について実体験をもとに書いてみる。
やりたい気持ちはずっとあった。でも最初は立ち止まっていた
長男が0歳の頃、一度英語の歌を聴かせていた時期があった。
ただ、「早期英語教育が発達障害の原因になるかもしれない」と聞いて、不安になり、一度すべてやめてしまった。
長男は言葉が早いタイプではなかったので、より慎重にならざるを得なかった。
一方、次男は0歳の頃から意味のある言葉が出始め、2歳になる頃には日本語で意思疎通がある程度できるようになっていた。
次男の日本語の発達を見て、「これなら大丈夫そうだ」と感じ、おうち英語を本格的に始めることにした。
「4歳までは英語の回路ができる」—— 友人の言葉に背中を押された
英語教育に携わっていた友人が、以前こんなことを話していたのを思い出した。
「4歳までは、英語をかけ流しておくだけで、脳に回路ができるんだよ」
それを聞いて、長男がちょうど4歳の今は“ラストチャンスかもしれない”と思った。
もともと、自分自身が「母語と同じように英語を身につけられたらいいな」と思っていたので、ようやくその思いに踏み出せた瞬間だった。
まずは“日本語に近い英語”から。しまじろうで導入
すでに日本語での会話が日常になっていたため、いきなり英語オンリーで進めるのは抵抗されそうだと感じた。
そこで、最初はベネッセの「しまじろうの英語教材」から始めることにした。
さすがは万人受けする教材だけあって、導入としてはぴったりだったと思う。
英語に抵抗がなくなったタイミングで、映像は英語だけに
英語へのハードルが下がったタイミングを見計らって、映像メディアはすべて「英語しか映らない」ように制御した。
実は、長男に自閉傾向の診断がついていたこともあり、それまでテレビもYouTubeも一切つけていなかった。
だからこそ、英語の映像コンテンツに対する食いつきはものすごかった。
英語=楽しいもの、という刷り込みが、ある意味パブロフの犬のように成立していたと思う。
不思議な光景が日常に。英語でつぶやく次男
次男は、まだ意味のある英語を話せない時期から、英語のリズムとイントネーションでブツブツ何かをしゃべっていた。
もちろん意味にはなっていなかったが、耳から入ってきた英語をそのまま口にしているようで、見ていて少し神秘的な印象すらあった。
遅めスタートだったからこそ、英語と日本語のバランスが取れた
始めたのが4歳だったおかげで、日本語の基盤がある程度できていたのは良かったと感じている。
というのも、その後かなり英語優位な状態になってしまって……もし0歳からずっと英語だけを入れていたら、逆に日本語の習得に支障があったかもしれない。
遅めだったからこそ、結果的にバランスが取れたのかもしれない。
母国語のように英語を身につけることは、日本にいても可能だった
私は子どもの頃から、「日本にいても英語を母語のように習得できたら面白いのに」と思っていた。
だからこそ、今の子どもたちの姿を見て、「あ、自分の仮説が立証された」と感じる瞬間がある。
英語が日常生活の一部になっていて、「なんで今英語で話してるんだっけ?」とふと思うこともあるが、今ではそれが当たり前になっており、不思議さも薄れてきた。
「遅すぎる」なんてことはなかった
我が家の場合、スタートは早くはなかったが、それでもここまで来ることができた。
英語に触れるのに、早すぎるも遅すぎるもない。
大切なのは、その子にとって自然なタイミングで、無理のないやり方で取り入れていくことだと思う。
「もう遅いかも」と思っている人ほど、安心してほしい。
むしろ、遅めのスタートだからこそ見えた景色も、たくさんある。


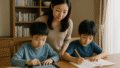

コメント