「寝かしつけ」に苦労している家庭は多いと思う。抱っこや背中トントン、添い寝などで毎晩時間をかけるのが当たり前になっている。けれど、我が家では寝かしつけを一度もしたことがない。
その理由は「照明の自動化」にある。夜は段階的に暗く、朝は段階的に明るくなるように設定しているので、親が声をかけなくても子どもが自然に行動できる。
特に、夜の照明が大事で、我が家は一般的な日本の家庭より暗めにしている。その理由については後述したい。
我が家の設定例
| 時間 | 照明の設定 | 子どもの様子・効果 |
|---|---|---|
| 6:15〜6:30 | 子ども部屋の照明が少しずつ点灯し、最後は一番明るくなる | 自然に目が覚めて、自分で起きる |
| 20:00〜20:15 | 照明が夜モードに切り替わり、暖色系の落ち着いた暗さになる | まだ寝る時間ではないが、身体が「今は夜だ」と認識する |
| 21:30〜22:00 | 照明が徐々に暗くなり、最終的に消灯 | 「もう寝る時間」と受け入れて布団に入る |
このように光が一日のリズムを示してくれるので、親が働きかけなくても自然に「寝る・起きる」の流れができている。
スマート照明とは何か(代表例:Hue)
スマート照明とは、時間やシーンに合わせて光を自動的に変えられる仕組みを持った照明のことだ。既存の照明器具に取り付けている電球をスマート電球に入れ替えるだけで導入できるので、特別な工事は必要ない。
スマホやAIスピーカーと連動して、明るさや色を自在に調整できるのが特徴である。
我が家では、この「自動で調整できる」という機能を活かして、夜は段階的に暗く、朝は少しずつ明るくなるように設定している。
スマート照明にもいくつか種類があるが、代表的なのがフィリップス社のHueだ。使い勝手という点ではHueが一番スムーズだと感じている。ただ、電球サイズのバリエーションはIKEAのTRÅDFRI(トロードフリ)もニッチなサイズの電球があり、Hueと互換性があるため、我が家では両方を併用している。
夜:段階的な消灯が寝かしつけを不要にした
親がスイッチで電気を消すと、子どもは「まだ寝ない」と抵抗してしまうことがある。特に幼児期は「自分の意思でコントロールしたい」気持ちが強いので、親が強制的に暗くすると反発が起きやすい。
しかしスマート照明を使って、毎晩同じ時間に段階的に暗くしていくと、それは“当たり前の流れ”として受け入れられる。親が声をかけなくても、子どもは自然に「寝る時間だ」と切り替えてベッドに向かう。
| 項目 | 親が手で消す場合 | スマート照明で自動消灯の場合 |
|---|---|---|
| 子どもの反応 | 「まだ寝ない!」と抵抗 | 流れとして受け入れる |
| 習慣化 | 親の声かけ次第 | 毎日同じ時間に環境で固定 |
| 親の負担 | タイミングを計って消灯 | 放っておいてもOK |
スマート照明は一度設定してしまえば毎晩自動で動くので、親は「消すタイミングを考える」「寝なさいと声をかける」といった作業が不要になる。
その分、夜の時間を自分のことに使えるし、眠りを妨げられることもない。
子ども側にとっても「自分の力で眠る」経験になり、環境に合わせて行動する自立につながっている。共働き世帯にとっては特に、この自動化の仕組みが毎日の負担を大きく減らしてくれると思う。
夜中:暗いままだから再入眠できる
夜中に子どもが目を覚ますことはある。でも照明が暗いままなので、「まだ夜だ」と理解して再び眠りにつく。
親を呼びに来ることもなく、結果的に大人の睡眠も守られる。これも「環境が子どもの行動を導く」効果のひとつだと感じている。
朝:自動点灯で自分から起きる
指定した時間になると、照明が段階的に明るくなる。
親が「起きなさい」と声をかけなくても、自分で起床できる。休日でも親より早く起きて、本を読んでいることもある。
夜と朝の照明の自動化が生活リズムを支えてくれるので、親が介入する必要がない。
「暗いと目が悪くなる」は思い込み
我が家の照明は夜は暗い。そんな話をすると、目が悪くなるのでは?と思う人は多いと思う。
けれど科学的には、暗い環境で本を読んだりテレビを見たりしても視力が恒久的に低下するという根拠はない。起こるのは一時的な疲れや見えにくさ(眼精疲労)だけであり、目が悪くなるわけではない。
むしろ夜に強い光を浴びることのほうが、睡眠ホルモンを妨げて眠りの質を下げることが分かっている。
日本の家庭照明は明るすぎる
実際に日本の家庭は200〜500ルクス程度で照らされているケースが多く、これは睡眠環境としては明るすぎる。
一方、ヨーロッパ(イギリス・EU)ではリビングの照度は50〜150ルクス程度が一般的で、ずっと抑えられている。数字で比較すると違いは明らかだ。
| 項目 | 日本の家庭 | 西欧(イギリス・EU基準) |
|---|---|---|
| 夜のリビングの照度 | 約200〜500 lx | 約50〜150 lx |
| 照明文化 | 「暗いと目が悪い」と信じて明るさを優先 | 暗さをくつろぎや眠気につなげる |
| 寝かしつけとの親和性 | 明るすぎて子どもが切り替えにくい | 暗さが自然な眠気を促し、ネントレと相性がよい |
※参考:日本の家庭照明の明るさ(200〜500 lx)【kaigo-postseven.com】、イギリス・EUの住宅照明基準(50〜150 lx)【ledkia.com】【ledrise.eu】
照明以外の前提条件(ジーナ式と子供部屋)
もちろん、照明だけで寝かしつけ不要になったわけではない。いくつかの前提条件が組み合わさっている。
我が家は赤ちゃん期にジーナ式を取り入れて、生活リズムを整えていた。その土台があったからこそ、スマート照明の自動化がスムーズにかみ合った。
また、子どもたちはリビングに隣接した子ども部屋で寝ている。リビングで過ごした延長でそのまま寝室に入る流れになるため、照明の切り替えが眠りにつながりやすい環境だった。
まとめ
寝かしつけ不要の理由は、親の努力ではなく「環境づくり」にある。
スマート照明を取り入れて光を自動でコントロールすることで、子どもは自然に眠り、朝は自然に起きる。親も手間から解放され、子どもの自立にもつながる。
夜は段階的に暗く、朝は段階的に明るく。光を味方につければ、寝かしつけの悩みはぐっと軽くなる。
参考
- 日本眼科学会・眼科医解説:「暗いところで本を読むと目が悪くなる」は医学的根拠なし【einlicht-opt.jp】
- Lettuce Club:「暗いところでの読書は視力低下の原因にはならない。ただし疲れ目にはなる」【lettuceclub.net】
- TBS:「暗い場所で本を読んでも視力は落ちないが、一時的に疲れることはある」【topics.tbs.co.jp】
- 西野精治『間違いだらけの睡眠常識』(スタンフォード大学 睡眠研究):家庭照明が明るすぎると睡眠に悪影響【shuchi.php.co.jp】




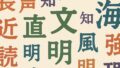
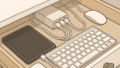
コメント