小学校の宿題の定番といえば「国語の音読」。でも、親としては正直、意味があるのか疑問を感じてきた。
長男も次男も、音読カードを自分から差し出すなんて一度もない。親が動かなければ一生やらない宿題で、正直、そのたびにランドセルをあさって引っ張り出すのは苦痛でしかなかった。サインをするたびに、「本当にこれに意味があるのか?」と疑問符ばかりが浮かんでいた。
次男の場合は、日本語の基礎がまだ怪しい部分もあるので、一応は取り組ませている。ただ、それでも学校の宿題としての音読にどこまで意味があるのか、やはり納得感は薄い。
音読の効果は研究で実証されている
「音読 宿題 意味ない」と感じる親は多いと思う。けれど、音読そのものには効果があることは心理学や教育学の研究で明らかになっている。
- 産出効果(production effect)
声に出して読むことで記憶の定着率が上がる。黙読よりも学習内容が残りやすい。 - 理解力の向上
音読では一語一語を処理するため、文章の意味理解が深まりやすい。 - 語彙や漢字の習得
特に小学生にとっては、繰り返し声に出すことで語彙力や漢字の定着につながる。
つまり、音読自体は科学的にも効果がある。
効果的な音読と学校の宿題の違い
では、効果的な音読という観点において、学校での宿題の音読はその条件を満たしているのだろうか。実はここに大きな差がある。
研究によれば、効果のある音読の条件は以下のように整理されている。
- 指導者の即時フィードバックつき音読(guided oral reading)
- 反復音読と目標設定
- 進捗のモニタリング
一方で、学校の音読宿題はどうか。
- 家庭で「読みっぱなし+親のサイン」になりやすく、即時の訂正や指導がない
- 繰り返しや目標が設計されていないため、形だけの課題になりやすい
- 読書ログ(音読カード)の必須提出は、子どもの読書意欲をむしろ下げることがある
- 小学校段階の宿題全般は学力向上との関連が弱いと報告されている
つまり、効果が出ると証明されている条件を満たしていないのが、今の学校宿題の音読なのだ。
宿題としての「音読」には疑問も多い
こうした研究と照らし合わせても、やはり学校の宿題としての音読には多くの疑問がある。
- 簡単すぎる文章を毎日読むだけでは、形だけになってしまう
- 難しすぎれば、意味がわからず機械的に読むだけになる
- 保護者のサインが必須で、親子にとって負担が大きい
- 子どもから音読カードを出すことはほとんどなく、親が動かなければ永遠にやらない
- 意義が見出せないものに毎日手間をかけるのは苦痛で、子どもの宿題というより親への宿題に感じられる
こうしてみると、音読が「意味のある学習」から「習慣的なノルマ」にすり替わってしまっている印象が強い。
宿題を出す習慣は大切、でも…
一方で、私自身が気にしているのは「宿題を提出する習慣」だ。
中学校に上がったとき、宿題を出さないことが内申点に響く可能性を考えると、やはり今のうちに習慣づけておくのは安全策だと思っている。
だからこそ「音読カードが原因で宿題を出さない子になってしまう」のは、いちばん避けたいところだ。
けれど実際には、音読そのものの意味よりも「カードにサインがあるかどうか」という形だけで評価される。
本質的でない理由で、子どもも親も毎日音読に取り組まざるを得ないという理不尽さがある。
本当に意味のある音読にするには
音読という学習法そのものには意味がある。問題は、学校の宿題としてのやり方だ。
私が考える改善案は、次のようなものだ。
- 読む文章を自由に選べるようにする
- 録音アプリなどを使い、親のサインに依存しない仕組みにする
- 読む目的(理解力を高めたい、漢字を覚えたい、発表練習をしたいなど)を明示する
こうすれば、音読宿題は「親の負担」ではなく「子どもの学び」に直結するものになるはずだ。
まとめ
- 音読には記憶や理解を助ける科学的効果がある
- ただし宿題としての音読は効果条件を満たしておらず、負担が大きい
- 一方で宿題提出の習慣づけは将来的に重要
- それでも本質的でない理由で毎日音読を強いられる理不尽さがある
- 改善の余地はあるが、意味のある音読をどう宿題に落とし込むかがポイント
「音読宿題は本当に意味あるの?」という疑問に対して、答えは「音読自体には効果があるが、今の宿題の形には疑問が多い」。
これが、私が親として長男・次男と向き合いながら感じてきた正直な結論だ。
参考・注釈
- National Reading Panel (2000). Teaching children to read. Evidence on guided oral reading の効果。
- MacLeod, C. M. et al. (2010). The production effect. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36(3).
- Therrien, W. J. (2004). Repeated reading meta-analysis. Review of Educational Research, 74(3).
- Brigham Young University study (2000). Required reading logs and reduced motivation.
- Cooper, H. et al. (2006). The effects of homework in different grade levels. Review of Educational Research, 76(1).
- Balli, S. J. (1998). Parent involvement in homework. Journal of Educational Research, 91(3).


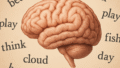

コメント