ここ数年で電子楽譜を使う人が増えている。
その流れを実際に目にして、自分も思い切って楽譜を電子化することにした。100冊以上あった紙の楽譜をまとめてPDFにしてiPadに収めたら、音楽ライフだけでなく暮らしの快適さまで変わった。
紙の楽譜は管理が大変だった
楽譜は気付けば100冊以上に増え、クローゼットの上段を占領していた。ピアノやバイオリン、室内楽などジャンルもさまざまで、持っている曲を把握するのも難しい。
ピアノのそばに置けないから、弾きたいときにすぐ取り出せない。「あの曲を弾きたい」と思っても探すのが面倒で諦めてしまうことが多く、結果として多くの楽譜が眠ったままになっていた。
楽譜を一気に電子化した方法
量が多すぎて自力でスキャンするのは非現実的だったので、スキャン代行サービスの「スキャンピー」を利用した。段ボールに詰めて送るだけで、すべてPDF化されて返ってくる。
コストは1万円程度。決して安くはないが、クローゼットが丸ごと片付き、100冊分の紙を手放せたのは大きな収穫だった。モノを減らすことで、部屋の空気まで軽くなった気がした。
楽譜用タブレットの選び方
電子化した楽譜を表示する端末選びは一番の悩みどころだった。調べると「楽譜は最低でも13インチ必要」という情報が多く、当時はiPad Pro(12.9インチ)しか選択肢がなかった。
結果的にiPad Proを選んだのは正解で、楽譜専用のつもりがPTAの作業やブログ執筆にも大活躍。iPhoneとの連携もスムーズで、使い方に迷わない安心感も大きかった。
最新モデルはオーバースペックだと思い、中古(iPadPro第4世代)を選んだ。6万円強ほどだったが、十分に元が取れる価値があった。
今ならiPad Airにも大画面モデルがあるので、より手軽に導入できると思う。実際にピアノ仲間に電子化を勧めたら、その日のうちにiPad Airを購入していた。
電子楽譜を快適に使うための必須アイテム
電子譜面を使い始めて実感したのは、譜めくりの快適さだ。譜めくり用のペダル(ページターナー)を導入したら、練習も本番もストレスなく進められるようになった。これは必須のアイテムだと思う。
さらに、タッチペンも導入した。Apple Pencilでなくても十分で、書き込みや修正が紙よりも快適。消しカスが出ないので、むしろ紙よりきれいに楽譜を保てるようになった。
愛用している電子楽譜アプリ
- PiaScore:無料で高機能。譜めくりペダルとの相性もよく、楽譜管理の定番。
- Henle Library:ヘンレ版の楽譜が紙より安く購入できる場合もあり、フィンガリングを複数切り替えられるのが特徴。自分の指使いが固まったら表示を消すこともできる。
紙と電子の違いを整理してみた
| 項目 | 紙の楽譜 | 電子楽譜 |
|---|---|---|
| 保管 | クローゼットを占領 | iPad一台に集約 |
| 取り出し | ピアノから遠く、探すのが面倒 | 検索ですぐに開ける |
| 譜めくり | 手でめくる必要あり | ペダルでスムーズ |
| 書き込み | 鉛筆と消しゴムで汚れやすい | ペンで書いてすぐ消せる、消しカスなし |
| コスト | 紙代・収納スペースが必要 | 端末と電子化費用は一度きり |
| レパートリー | 眠ったままになりがち | 思い立ったらすぐ弾ける |
電子化して得られた一番のメリット
電子化して一番うれしかったのは、昔よく弾いた曲や、ふと思い出した曲をすぐに取り出せるようになったことだ。眠っていた楽譜が復活し、レパートリーが広がった。
そして、100冊の紙を手放してiPad一台に集約できたことは、音楽のためだけでなく暮らし全体の身軽さにもつながった。
まとめ
電子楽譜に移行したことで、
- 楽譜がすぐに取り出せる
- 譜めくりや書き込みが快適
- レパートリーが復活・拡大
- 紙100冊を手放して部屋がすっきり
導入コストはスキャン代行で1万円、iPad Proの中古で6万円程度。だが、それ以上に「持ち物を減らして身軽になれる」というミニマリスト的な効果が大きかった。
電子楽譜は便利なツールであると同時に、暮らしをシンプルに整えるための一歩でもあると感じている。

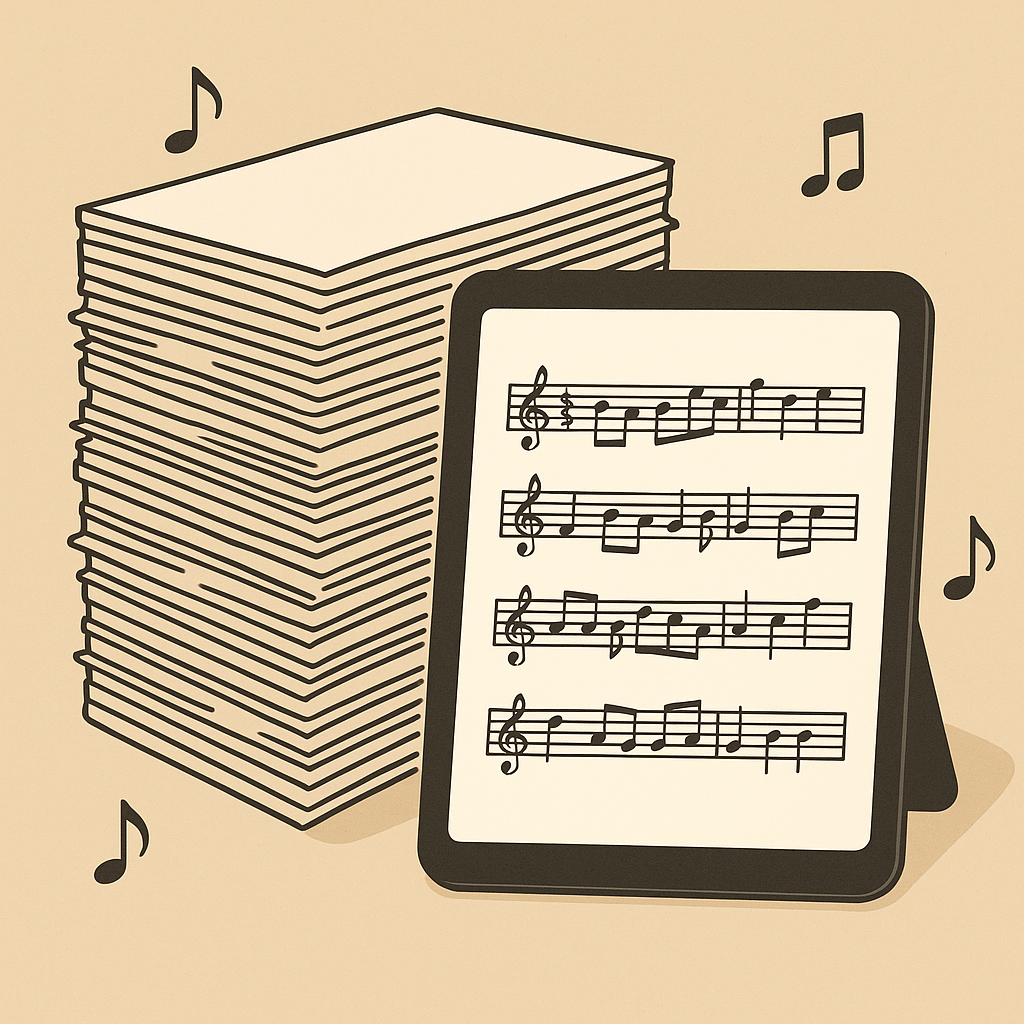



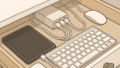

コメント