最近、息子が弟との会話の中で「sigh…」とつぶやいていた。日本語なら「はぁ…」とため息を吐く場面だ。英語の漫画で見かけた表現をそのまま口にしていたことに気づき、言語と表現の違いについて改めて考えた。
“sigh…”はセリフではなく描写だ
英語の漫画では、ため息の場面に “sigh…” と書かれていることがある。しかし英語圏の日常会話で「sigh」と声に出して言うことは基本的にない。あくまで「ため息をついた」という動作や状況を文字で示す描写だ。実際の会話では、ため息の音を出してから言葉を続けることになる。
日本語漫画の強みは「音」で伝える表現
日本語の漫画は擬音語・擬態語が豊かだ。「はぁ…」「ざわざわ」「ドキッ」 のように、音だけで情景や感情の細かなニュアンスを伝える仕掛けが随所にある。絵と文字が相互に補完し合い、読者は少ない言葉で状況の空気を直感的に掴める。
英語漫画ならではの良さもある
一方で、英語で作られた漫画やグラフィックノベルは別の魅力を持つ。セリフ回しやリズム、ユーモアの取り方が異なり、英語圏の文化や言語感覚に直に触れられる。語彙や表現の使われ方、会話の省略の仕方など、学習素材として価値が高い。
実践例:我が家ではEpic!を活用している
近年、洋書は値が張るため、英語の漫画を読ませる際はサブスク型のサービスを活用している。月額で多くの英語絵本やコミックにアクセスできるため、量を確保しやすい。英語の表現や感覚に触れる機会が増え、子どもの語感形成に役立っている。
結論:媒体と言語を意図的に選ぶ
息子が口にした「sigh…」は、言語表現の違いを身近に感じさせる出来事だった。日本語の漫画は日本語で読むことで、擬音語や語感の微妙な表現をそのまま伝えられる。英語の漫画は英語で読むことで、言語文化のリズムや感覚を自然に学べる。翻訳版は便利だが、原作で読む体験はそれぞれの言語の呼吸を教えてくれる。
漫画を読み分けることは、ことばの学びと文化理解を同時に進める有効な方法だ。日本語の漫画は日本語で、英語の漫画は英語で。子どもには両方の世界を楽しませたい。

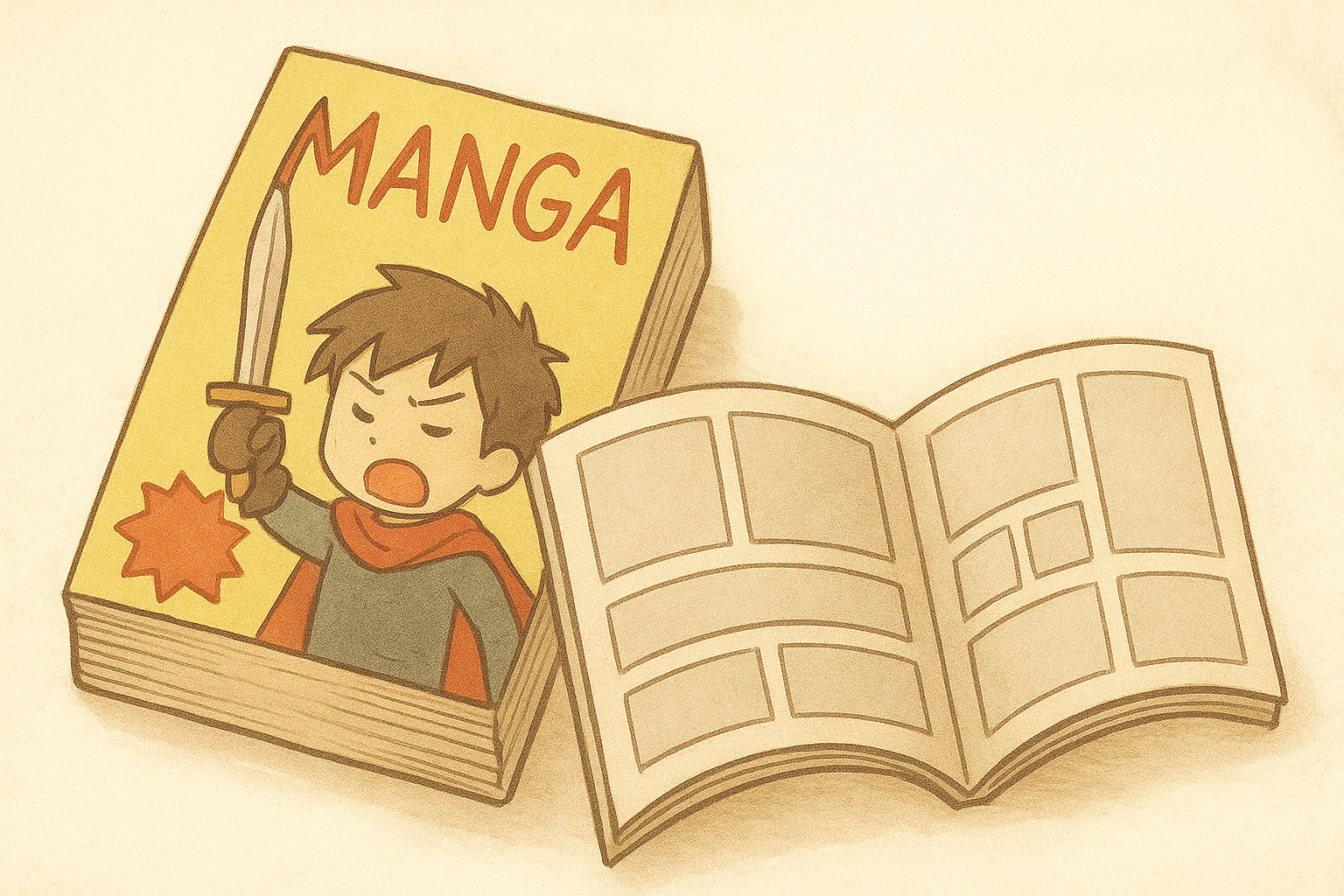
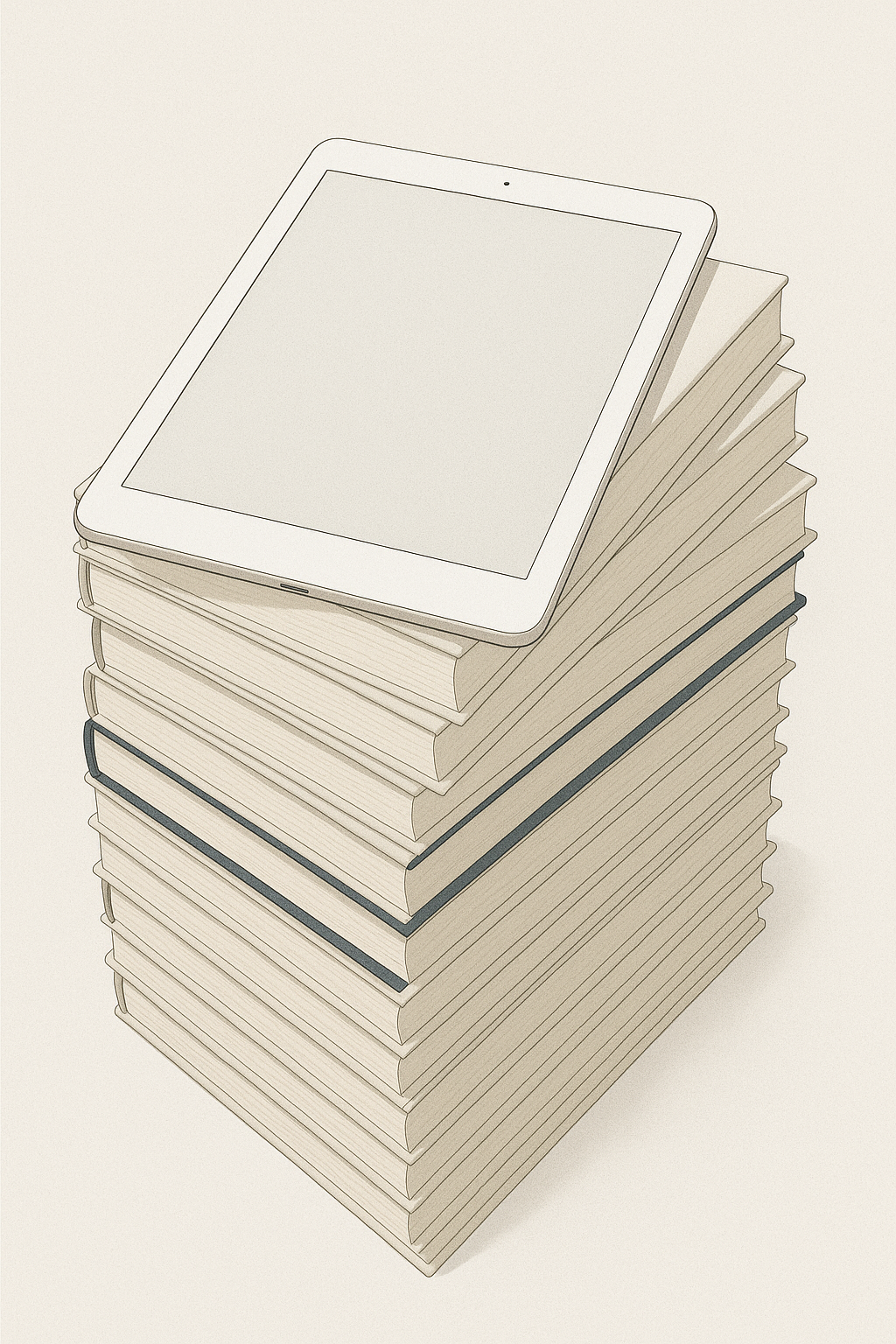

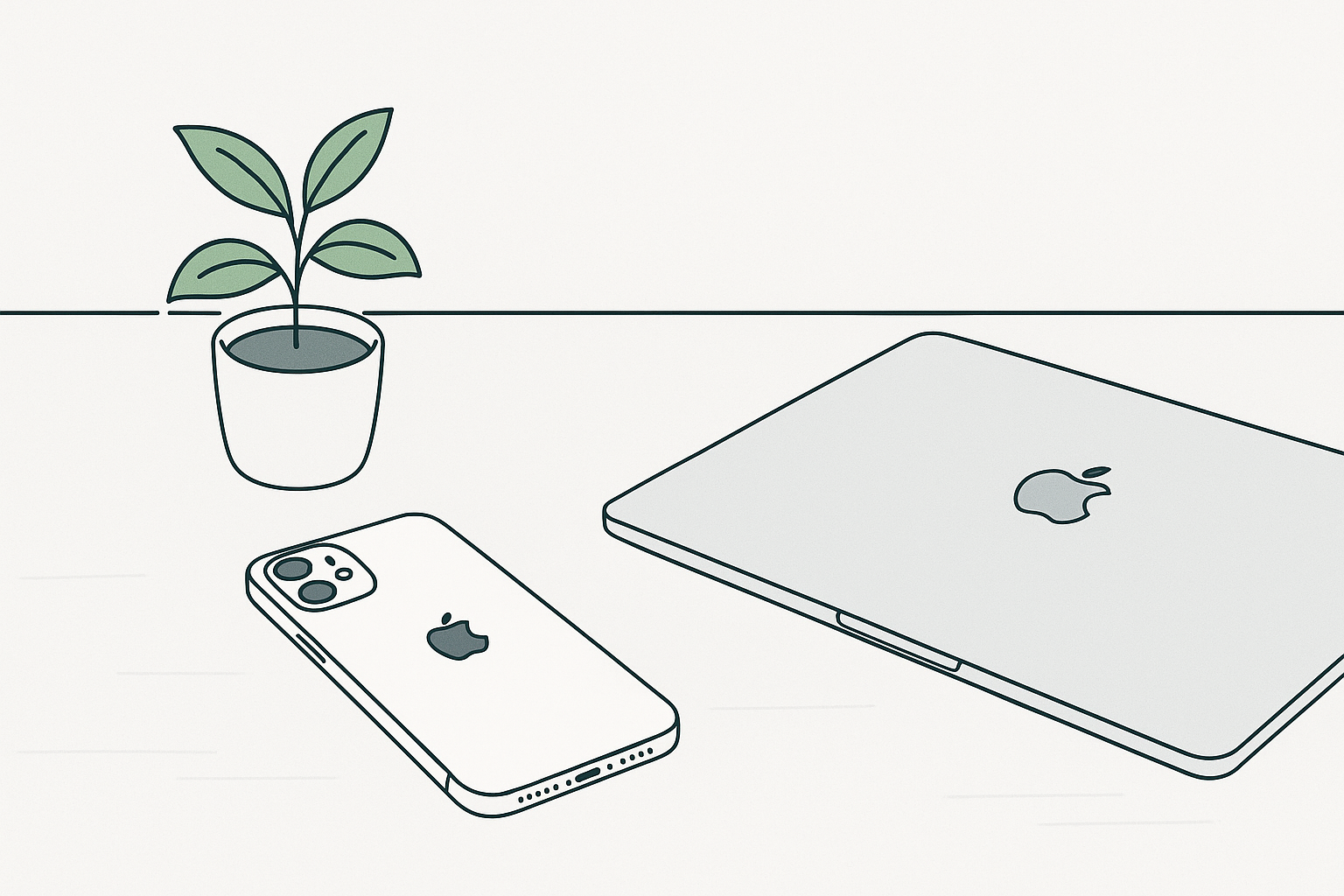
コメント