スマイルゼミのコアトレは「進まない」「途中で止まってしまう」と悩む家庭が多い。我が家でも同じ壁にぶつかり、何度も挫折しかけた。けれども見通しを立てる工夫を取り入れてから、コアトレが続けられるようになった。この記事では、その具体的な工夫と考え方をまとめておく。
コアトレが進まない子が多い理由
スマイルゼミのコアトレには、次のような仕組み上の特徴がある。
| レベル | 進む条件 |
|---|---|
| 問題群 | 全問正解しないと次がアンロックされない |
| 単元 | 前の単元を終えないと後の単元が開かない |
| ステージ | 全単元をクリアしないと次に進めない |
このため、途中で間違えると残りの問題をやめてしまい、最初からやり直すという非効率な取り組みになりやすい。解説を読まずに同じ問題を繰り返すため、その単元の全容が見えないままになる。結果としてクリアまでに膨大な時間がかかり、諦めにつながることがある。
絶対にやってはいけないこと
我が家の失敗例としては、1日のノルマを「○個クリアする」と決めてしまったこと。このやり方だと、間違えた瞬間に残りをやらずに最初からやり直す癖がつきやすく、学習効率が下がってしまう。非効率なループを繰り返し、やがて挫折につながった。
じゃあどうすればいい?
- 間違っても最後までやる
- その日にクリアできなくても翌日また挑戦する
こうしておくと「やり切った感」が残り、少しずつでも継続しやすくなる。ただ、このままだと「どれだけやればいいのか」「いつ終わるのか」という見通しが立たない。行き当たりばったりになり、モチベーションは上がりにくい。
見通しを立てて逆算する
そこで取り入れたのが見通しを持つこと。まずはゴールを決める。
我が家の場合
長男は小4の直前からコアトレを始めたが、そのときのステージは3(小学校低学年相当)。ここから「今年度中にステージ7(学年相当)まで進めたい」という目標を親子で合意した。
実績から分かったこと
| 教科 | 1単元あたりの平均試行回数 | 問題群数(平均) |
|---|---|---|
| 国語 | 約3回 | 約5個 |
| 算数 | 1〜2回 | 約5個 |
逆算の計算式
(単元数 × 問題群数 × 目標ステージ数 × 平均試行回数) ÷ 残り日数
この式で「1日に必要なおおよその試行回数」が見えるようになった。
目標の調整
- 国語は計算上、1日5回試行が必要になる見通しだった
- ただし負荷が大きすぎるため、国語はステージ6まで、算数はステージ7までを今年度の目標に修正
- その結果、国語は「1日5個進める」ではなく、「1日3個進める」に軽減
こうして月ごとの進度目安も整理し、状況に応じて柔軟に修正するスタイルに落ち着いた。
ビハインドでも先取りでも同じ
我が家は出遅れたところからのキャッチアップだったが、先取りで使いたい家庭にも同じ手法は応用できる。
- いつまでにどのステージまで進めたいか先に決める
- 過去の実績から「1単元をクリアするのに何回必要か」を見積もる
- そこから逆算して、1日の試行回数を目安にする
大事なのは、その日のクリアにこだわらないこと。 「クリアするまでやり直し」だと、途中で諦めたり最初からやり直す癖がつき、効率が悪くなる。
行き当たりばったりとは違う
計画を柔軟に見直すことは必要だが、「1日○個やっていればそのうち進む」といった行き当たりばったりの進め方では、ゴールが見えずモチベーションが保てない。重要なのは、ゴールを親子で共有し、そこから逆算して日々の取り組みを設計することだ。
見通しを持つことで「やれば到達できる」という安心感が生まれ、子どもが自分から取り組む力になる。
見通しを持つことの効果 — 研究からの裏付け
- ゴール設定理論(Goal Setting Theory):明確で具体的、かつ適度にチャレンジングな目標は達成率を高める。
- 自己調整学習(Self-Regulated Learning):目標 → 計画 → 実行 → 評価 → 調整という循環が、継続と理解定着につながる。
- 「終わりが見えない」状態はモチベーションを下げ、中断につながるという指摘が複数ある。
つまり、「いつまでにどこまでやる」と先に決め、そこから逆算して計画を立てることは、理論的にも効果がある方法だと考える。
まとめ
スマイルゼミのコアトレは、先取りにも復習にも、そして苦手克服にも使える優れた教材だと思う。途中で「進まない」と挫折してやめてしまうのはもったいない。
見通しを持ち、ゴールを親子で共有して逆算すれば、無理なく続けやすくなり、子ども自身も安心して取り組める。
出典
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist, 57(9), 705–717.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64–70.
- Panadero, E. (2017). A Review of Self-Regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research. Frontiers in Psychology, 8, 422.
- Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment. Psychological Science, 13(3), 219–224.
- Capelle, J. D., et al. (2023). Deadlines make you productive, but what do they do to your well-being? PLOS ONE, 18(11): e0294498.
- Kivetz, R., Urminsky, O., & Zheng, Y. (2006). The Goal-Gradient Hypothesis Resurrected. Journal of Marketing Research, 43(1), 39–58.
- Brady, A. C., et al. (2022). Self-regulation of time: The importance of time estimation and task beliefs. Metacognition and Learning, 17(3), 797–826.


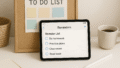
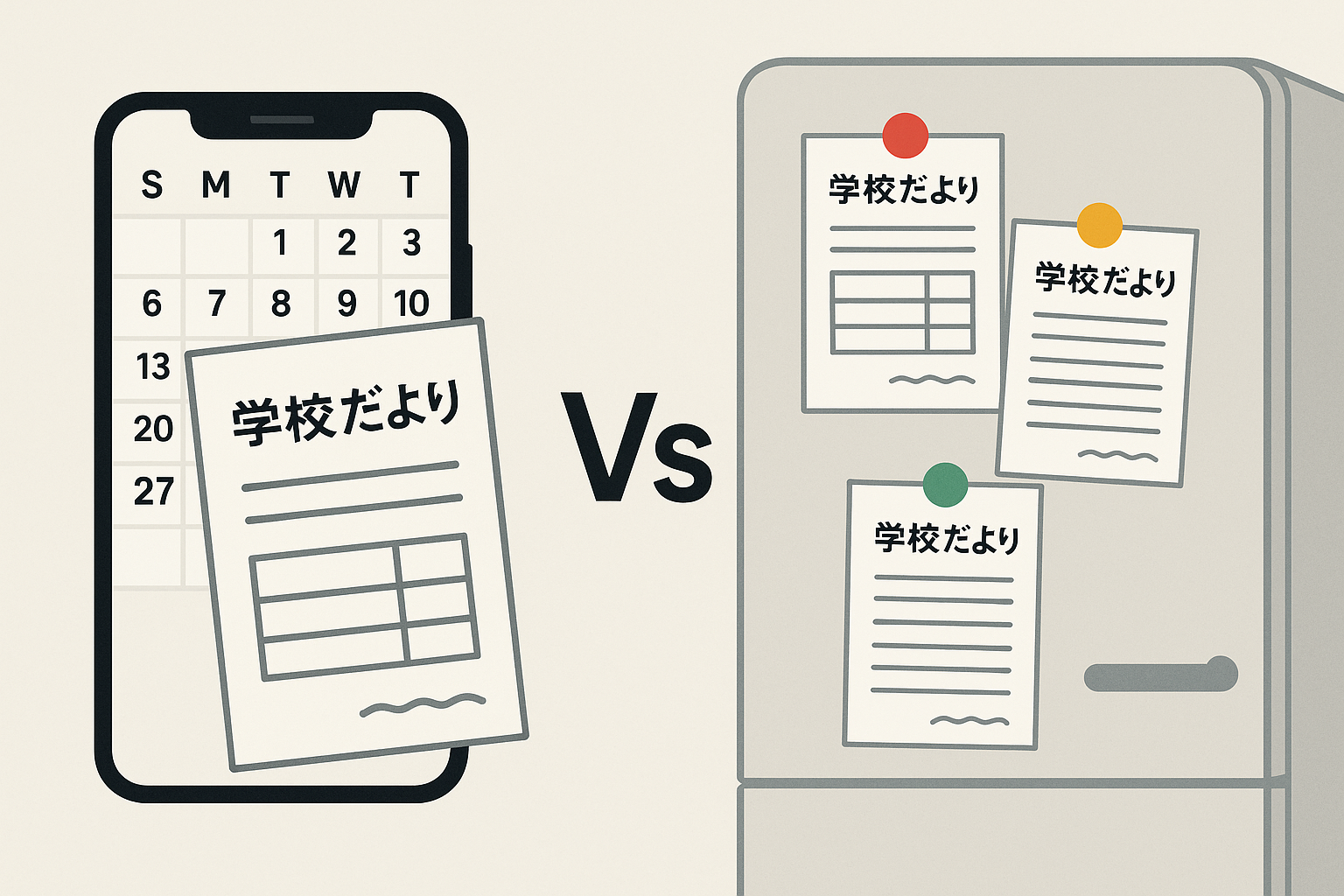
コメント